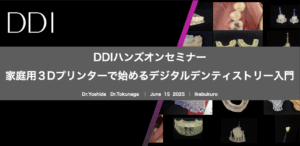はじめに
2025年4月、ドイツのケルンで開催された国際歯科用品展示会(IDS:International Dental Show)に参加してきました。IDSは2年に1度開催される世界最大規模の歯科業界の展示会で、最新の技術、製品、そして業界のトレンドが一堂に会する重要なイベントです。今回の参加では、特にデジタル技術、3Dプリント技術、そして新しいマテリアルに焦点を当てて展示を見学してきました。8年前にも同じ展示会を訪れた経験がありますが、今回感じたのは歯科業界におけるデジタル変革の加速でした。物理的な展示物から、ソフトウェアやAI技術を中心とした展示への大きな変化、そして日本市場が直面している課題と機会について、現地で得た生の情報をお伝えします。

展示会の全体印象:デジタル化が変えた展示のあり方
今回のIDSで最も印象的だったのは、展示のあり方そのものが大きく変化していたことです。8年前と比較すると、圧倒的に物理的な展示物の量が少なくなっていました。もちろん製品やブースは存在するのですが、従来のような「触って確かめる」タイプの展示から、PCの画面でプレゼンテーションを行ったり、画面を操作して3Dモデルを回転させたりといった、ソフトウェアを中心とした展示が大幅に増加していました。
これは単なる展示手法の変化ではなく、歯科業界そのもののデジタル化を象徴する変化だと感じました。AIを活用したソリューション、クラウドベースのワークフロー管理システム、そしてバーチャルリアリティを使った患者説明ツールなど、従来の物理的な機器だけでは表現できない価値を提供する製品やサービスが主流になってきているのです。
来場者数についても変化を感じました。以前であれば、人混みで身動きが取れないほどの混雑でしたが、今回は比較的スムーズに会場内を移動することができました。公式の来場者数は確認していませんが、体感的には以前より少ない印象でした。ただし、これが業界の縮小を意味するのではなく、むしろ参加者の質的な変化、つまりより専門性の高い来場者が増えているのかもしれません。
特定のブースでは依然として行列ができていました。特にVRゴーグルを使った体験型のデモンストレーションや、新しい技術のライブプレゼンテーションが行われているブースには多くの人が集まっていました。これは、単に製品を見るだけでなく、実際に体験できる価値を求める来場者のニーズの変化を表していると考えられます。

3Dプリント技術の進歩:マテリアルの革新が開く新たな可能性
3Dプリント技術は、今回のIDSでも大きな注目を集めていました。特に印象的だったのは、新しいマテリアルの登場です。会場の至る所でレジンボトルが展示されており、実際に出力されたサンプルを手に取って確認することができました。
従来のマテリアルと比較して、明らかに密度が高く、重量感のあるサンプルが多数展示されていました。大きさの割に重量があり、「しっかりしている」という印象を受けるものが増えています。もちろん、実際の臨床での使用感は使ってみなければ分からない部分もありますが、少なくとも物理的な特性においては大きな進歩を感じることができました。
マルチカラー出力についても展示されていましたが、これはまだ実用化には時間がかかりそうな印象でした。技術的には可能であっても、臨床での実用性や精度の面で、もう少し発展が必要だと感じました。
特に注目すべきは、splint ray社のヨーロッパ部門が今回のIDS期間中に200台もの3Dプリンターを販売したという話です。これは驚異的な数字で、歯科業界における3Dプリント技術への需要の高さを物語っています。pro2なのか、他のモデルも含めた総数なのかは定かではありませんが、いずれにしても非常に高い関心度を示しています。
3Dプリント技術の進歩は、単に新しい製造方法を提供するだけでなく、歯科治療のワークフロー全体を変革する可能性を秘めています。デジタルスキャンから設計、そして最終的な製品の出力まで、すべてがデジタル環境で完結できるようになることで、より精密で効率的な治療が可能になります。また、患者一人ひとりに完全にカスタマイズされた治療器具や補綴物の製作も、より身近なものになってきています。

スキャニング技術の小型化とモバイル化の波
スキャニング技術の分野では、小型化が大きなトレンドとなっていました。特に中国や台湾のメーカーを中心に、従来よりもコンパクトなスキャナーが多数展示されており、これらの技術革新は日本の歯科診療環境にとって非常に重要な意味を持っています。
インビザライン社の新しいスキャナーも注目を集めていました。6つのカメラを搭載したこのデバイスは、確かに非常にきれいな画像を撮影することができます。実際に触ってみると、その精度の高さを実感できました。ただし、使い勝手の面では改善の余地があると感じました。特に遠心部の撮影が困難で、先端部分がもう少し曲がっていれば使いやすくなるのではないかと思いました。
しかし、最も興味深かったのは、スマートフォンを活用したスキャニング技術の進歩です。iPhoneなどのスマートフォンを使ったフォトグラメトリー技術が、臨床応用可能なレベルまで発達してきています。これは小型化の最たる例であり、従来の大型で高価なスキャニング装置に代わる可能性を秘めています。
フォトグラメトリーを使ったスキャニングは、もはや「安価な代替手段」ではなく、実用的な選択肢として認識されるようになってきました。スマートフォンの高性能化により、十分な精度での3Dスキャンが可能になっており、これにより診療所での導入コストを大幅に削減できる可能性があります。
さらに興味深いのは、モーションキャプチャー技術のスマートフォンへの応用です。iPhoneでモーションキャプチャーができるアプリも既に存在しており、これを顎運動測定に応用できれば、従来の大型で高価な顎運動測定装置に代わる解決策となる可能性があります。1台の端末で複数の機能を実現できれば、診療所にとっては大きなメリットとなります。

AI技術の歯科応用:顎運動測定からワークフロー管理まで
AI技術の歯科分野への応用も、今回のIDSで大きな注目を集めていました。特に顎運動測定の分野では、従来の物理的な測定方法
から、AIを活用したシミュレーションやトラッキング技術への移行が進んでいます。
従来の顎運動測定は、バイトを取ったり、専用の装置を使ったりと、患者にとって負担の大きい手法が主流でした。しかし、AIを使った顎運動シミュレーションや、実際の顎運動をリアルタイムでトラッキングして数値化し、CADソフトウェアに移植する技術が登場してきています。
DiGMA、ナソヘキサ、キャディアックスなどの従来からある顎運動測定装置も展示されていましたが、これらの装置の多くは依然として大型で、日本の診療環境には導入が困難な場合が多いのが現実です。装置のサイズは、デジタル歯科を推進する上での重要な課題の一つとなっています。
一方で、AIを活用することで、より小型で使いやすい顎運動測定システムの開発が進んでいます。これらのシステムは、従来の大型装置と同等の精度を保ちながら、より手軽に使用できる可能性を秘めています。
AIの応用は顎運動測定だけにとどまりません。診断支援、治療計画の立案、ワークフロー管理など、歯科診療のあらゆる場面でAI技術が活用され始めています。特に画像診断の分野では、AIによる自動診断支援システムが実用化レベルに達しており、診断精度の向上と診療効率の改善に大きく貢献しています。
また、患者とのコミュニケーションにおいてもAI技術が活用されています。治療計画の説明や、治療後の予測結果の可視化など、患者の理解を深めるためのツールとしてAIが重要な役割を果たしています。
日本市場が直面する課題:互換性とコストの壁
今回のIDSを通じて、日本の歯科業界が直面している課題についても深く考えさせられました。最も大きな問題の一つは、異なるメーカー間でのシステムの互換性の欠如です。
一般的に歯科では、各メーカーが独自のシステムを提供しており、それぞれが専用のPCやソフトウェアを必要とします。スキャナーメーカーが違えば、使用するソフトウェアも異なり、連携している技工所もそれぞれ異なるシステムを使用しているという状況が一般的です。これは、デジタル歯科の普及を阻害する大きな要因となっています。
この問題は、診療所にとって大きな経済的負担となります。複数のシステムを導入するためには、それぞれに対応したPCを購入し、異なるソフトウェアのライセンスを取得し、スタッフの教育も個別に行う必要があります。これでは、デジタル化のメリットよりもコストの方が大きくなってしまう場合も少なくありません。
理想的には、1台の端末ですべての機能を実現できるシステムが求められています。スキャニング、設計、3Dプリント、そして技工所との連携まで、すべてが統一されたプラットフォーム上で行えれば、導入コストの削減と業務効率の向上を同時に実現できます。
また、機材のサイズも日本市場特有の課題です。ヨーロッパやアメリカの診療所と比較して、日本の診療所は一般的にスペースが限られています。そのため、大型の装置は物理的に導入が困難な場合が多く、小型化は技術的な要求であると同時に、市場ニーズでもあります。
これらの課題を解決するためには、業界全体での標準化の推進と、日本市場の特性を理解した製品開発が必要です。また、メーカー間の協力により、互換性のあるシステムの構築を進めることも重要です。
バーチャルとリアルの融合:次世代歯科治療の展望
今回のIDSで特に印象的だったのは、バーチャル世界とリアル世界を行き来できる技術の展示でした。デジタルデータから実物への変換、そしてその逆の変換が、より自然で効率的に行えるようになってきています。
3Dプリント技術の進歩により、デジタル設計されたバーチャルな補綴物や治療器具を、高精度で実物として出力することが可能になりました。同時に、高精度スキャニング技術により、実物をデジタルデータとして正確に取り込むことも容易になっています。この双方向の変換技術により、治療計画の立案から実際の治療まで、シームレスなワークフローが実現されつつあります。
特に注目すべきは、患者とのコミュニケーションにおけるバーチャル技術の活用です。VRゴーグルを使った治療説明システムでは、患者が自分の口腔内の3Dモデルを実際に見ながら、治療計画を理解することができます。これにより、従来の2D画像や模型では伝えきれなかった情報を、より直感的に患者に伝えることが可能になります。
また、治療シミュレーション技術も大きく進歩しています。治療前の状態から治療後の予想結果まで、リアルタイムでシミュレーションを行い、患者と歯科医師が一緒に最適な治療計画を検討することができるようになってきています。
これらの技術は、単に新しいツールを提供するだけでなく、歯科治療そのもののあり方を変革する可能性を秘めています。より精密で予測可能な治療、患者の理解と満足度の向上、そして治療効率の大幅な改善など、多方面にわたってメリットをもたらすことが期待されています。
さらに、遠隔診療や遠隔指導への応用も考えられます。高精度なデジタルデータを共有することで、専門医による遠隔での診断支援や、若手歯科医師への教育指導なども可能になるでしょう。

今後の展望:歯科業界のデジタル変革が加速する
今回のIDS 2025を通じて、歯科業界のデジタル変革が確実に加速していることを実感しました。8年前と比較した変化の大きさを考えると、今後2年間でさらに大きな変革が起こることは間違いありません。
技術的な観点から見ると、AI、3Dプリント、スキャニング技術のそれぞれが個別に進歩するだけでなく、これらの技術が統合されたソリューションが増えてくることが予想されます。例えば、AIによる診断支援とスキャニング技術を組み合わせた自動診断システムや、3Dプリントと顎運動測定を統合したカスタマイズ補綴物製作システムなどが実用化されるでしょう。
小型化とモバイル化のトレンドも継続すると考えられます。スマートフォンやタブレットを活用したソリューションがさらに発展し、従来の大型装置に代わる選択肢として確立されていくでしょう。これにより、特に日本のような限られたスペースでの診療環境において、デジタル歯科の導入がより現実的になります。
標準化の動きも重要です。現在の互換性の問題を解決するため、業界全体での標準規格の策定が進むことが期待されます。これにより、異なるメーカーの製品間での連携が可能になり、診療所にとってより柔軟で経済的なシステム構築が可能になるでしょう。
教育面でも大きな変化が予想されます。デジタル技術の進歩に伴い、歯科医師や歯科技工士の教育カリキュラムも大幅に見直される必要があります。従来の手技に加えて、デジタルツールの操作やデータの解釈など、新しいスキルセットが求められるようになります。
患者体験の向上も重要なポイントです。より精密で予測可能な治療、短縮された治療期間、そして改善されたコミュニケーションにより、患者満足度の大幅な向上が期待できます。これは、歯科医院の競争力向上にも直結する重要な要素です。

おわりに
IDS 2025への参加を通じて、歯科業界が大きな変革期にあることを改めて実感しました。デジタル技術の進歩は、単に新しいツールを提供するだけでなく、歯科治療の根本的なあり方を変えようとしています。
日本の歯科業界にとって、これらの変化は大きな機会であると同時に、克服すべき課題でもあります。互換性の問題、コストの課題、そして教育の必要性など、解決すべき問題は多岐にわたります。しかし、これらの課題を乗り越えることができれば、より質の高い歯科医療の提供と、業界全体の発展が実現できるでしょう。
次回のIDS 2027では、今回見た技術がどのように発展し、実用化されているかを確認するのが楽しみです。歯科業界のデジタル変革は始まったばかりであり、今後の展開に大いに期待しています。
---